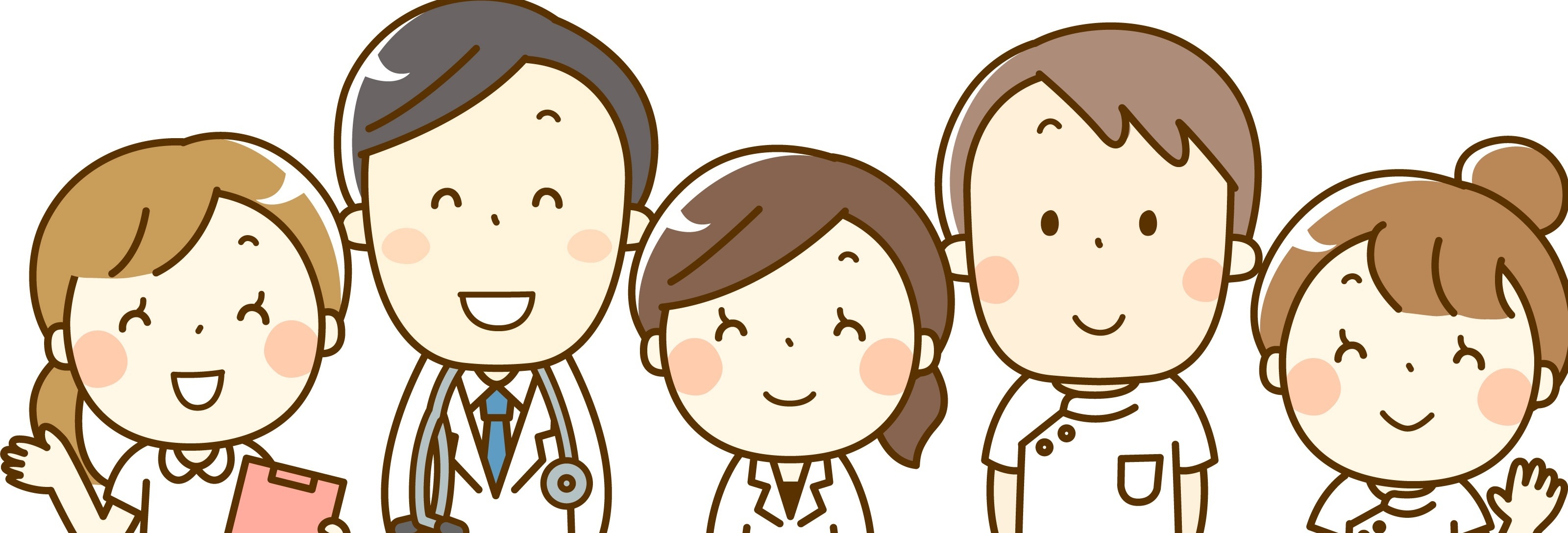博士課程の概要
- 博士課程(看護学専攻)
- 博士課程(健康科学専攻)※令和8年度より募集停止
- 博士課程(後期)アドミッションポリシー,カリキュラムポリシー,ディプロマポリシー
- 博士論文担当教員と研究指導領域・テーマ例 [PDFファイル/220KB]
- 博士論文(博士学位論文の要旨および審査結果)
博士課程(看護学専攻)
博士(後期)課程では、看護学の教育、研究に携わることのできる人材を育成することを主な目的としています。本学では、博士(後期)課程では、看護基礎科学領域と看護専門科学領域の二つの領域を設定し、看護学の基盤となる領域の教育および専門領域の教育を教授、研究できる人材を育成します。
看護基礎科学領域
看護基礎科学領域では、看護の対象者を身体的、精神的、社会的側面など多面的な視点から理解できる基盤的事項を教授、研究します。
基礎科目としては、生命病態学、健康増進科学、保健情報科学、精神保健学、放射線保健学を設け、生命の尊厳、人体の構造・機能、さまざまな環境原因に対する生体の反応、人、人間との係わりなどをより深く理解するとともに、ヘルスプロモーションの理論と実際等を学ぶことで、看護職としての役割を認識させます。また、看護に関する情報の取り扱いなどを理解し、看護研究の結果の分析と解釈などを通して、応用能力を身につけEBNに基づいた実践能力を発揮し、実践現場でのリーダーシップをとれる能力を育成します。
看護専門科学領域
看護の専門科学領域では、専門領域の看護をより深く教授、研究します。
専門科目としては、生活支援看護学、看護管理学、生殖看護学、発達看護学、国際看護学を設け、将来、それぞれに関連した分野の教育や研究を担当できる専門家および、関連分野の臨床現場等で活躍できる人材を育成します。
博士課程(健康科学専攻)
健康科学専攻博士(前期・後期)課程では、看護職のみならず非看護職で、さまざまな「健康科学」の教育、研究に従事できる人材の育成できる体制とするために、複数の領域からなる専門領域を設定し、健康科学の基盤となる領域の教育および専門領域の教育を教授、研究できる人材を育成します。
詳しい専攻領域については,こちらをご覧ください。
博士課程(後期)アドミッションポリシー,カリキュラムポリシー,ディプロマポリシー
博士課程(後期):アドミッションポリシー
看護学専攻あるいは健康科学専攻において、看護学あるいは健康科学の探究を目指す、以下のような入学者を求め、アドミッションポリシーを定める。
- 看護学あるいは健康科学を探求するために必要な基礎学力および研究力を有する人材
- 高い問題意識を持ち、研究テーマを自ら探究し設定する力を有する人材
- 看護学あるいは健康科学の発展に貢献できる人材
博士課程(後期):カリキュラムポリシー
博士課程後期 看護学専攻
1)教育課程の編成方針
看護学専攻に看護基礎科学、看護専門科学の2つの専攻領域を設置し、入学者はいずれかの専攻領域を選択します。
DP1.「研究成果の論理的説明能力」を習得するために、各自の専攻領域の特論および演習を通して、専攻領域に関連する幅広い専門的知識を養成します。加えて隣接する施行領域の特論も履修し、専門領域の知識をより広範な文脈に位置づける専門的リテラシーを研鑽します。
DP2.の研究能力を習得するために、主指導教員とこれを補佐する副指導教員の指導を受け、原著論文抄読などを通して研究分野に関連する幅広い専門的知識を身につけると共に、各自の研究を立案・遂行・論文発表して研究管理能力を習得します。
1)学修方法・学修過程
特別研究を進める過程で、原著論文抄読などを通して研究分野に関連する幅広い専門的知識を身につけると共に、高い専門性をもった研究力を養成します。さらに、研究計画報告会、研究中間報告会、査読付学術誌への論文投稿等を経て、論理的な研究発表やディスカッションなど研究成果の論理的説明能力を習得します。
2)学修成果の評価
特論と演習の学修成果は、各科目において評価します。特別研究については、査読付き学術誌での投稿受理を必要条件とする博士論文を提出し、その学術的価値、新規性、応用的価値等を指導教員以外の審査員が総合的に審査して、合格とします。ただし、審査では、研究成果の論理的説明能力、研究分野に関連する幅広い専門的知識、高い倫理性などを有しているかも評価します。
博士課程後期 健康科学専攻
1) 教育課程の編成方針
健康科学専攻に、健康生理学、環境健康科学、健康運動科学、放射線健康科学、健康情報科学、メンタルヘルスの6つの専攻領域を設置し、入学者はいずれかの専攻領域を選択します。
DP1.「学内外での研究発表の機会を通して身につけた、論理的に構成された発表およびディスカッションができるなど研究成果の論理的説明能力を有する」を身に付けるため、各専攻領域のカリキュラムには演習を入れています。また、論文レビュー報告会(D1)、論文計画報告会(D1)、論文中間報告会(D2)、研究成果報告会(D3)での発表機会を設けています。
DP2.「査読付き学術誌での投稿受理を必要条件とする博士論文を提出し、その学術的価値、新規性、応用的価値等を審査員が総合的に審査して、合格とする。ただし審査では、研究成果の論理的説明能力、研究分野に関連する幅広い専門的知識、高い倫理性などを有しているかも評価する」を満たすために、課題研究(博士学位論文)を課しています。また、本論文以外に、本論文の内容を含む査読付きのジャーナルに掲載された副論文(和文なら2編、英文なら1編)の提出を義務づけています。さらに、博士学位論文の審査では、「博士論文審査のためのクライテリア」に基づき、3名の審査委員が上記の点を評価します。
2) 学修方法・学修過程
この専攻は、6専攻領域に分かれており、それぞれに具体的な教育内容が異なっています。このため科目編成も異なっており、各科目の内容についてはシラバスに明示してあります。共通しているのは、はじめに講義を中心とした特論、それから学生がより積極的・主体的に参加できる形式の演習を受講するように構成されていることです。講義では各専攻領域の最先端の科学的知見が講義され、幅広い専門的知識や研究倫理等も学びます。この中で現象を科学的に捉える姿勢や科学的に分析する方法も学びます。また、演習では学生が自ら調べたり考えたりしたことを発表し、それをもとにして討論しながら知識を深めたり、論理的な思考を経験します。特別研究(博士学位論文)では論文の指導教員を2人体制とし、周辺領域を専門とする教員を副指導教員に入れることで、幅広い専門的知識を身につけられます。一方、学位の取得要件に副論文の提出を要件に入れています。このため、学生は博士論文の研究成果を筆頭著者として査読付き学術雑誌に投稿して審査を受け、審査員の指摘に対応して論文化する能力を磨くと同時に、学術的価値、新規性、応用的価値、応用的価値等の評価を学会から評価されます。そして、学内の学位論文審査では、明確な「博士論文審査のクライテリア」に基づいて審査が行われ、論理的説明能力、研究分野に関連する幅広い専門的知識、高い倫理性等についても評価されます。
正規の授業以外でも、高い研究倫理性を身につけるために、毎年、一般財団法人公正研究推進協会が開発した研究倫理教育eラーニングであるe-APRINの受講を義務づけており、博士学位論文も倫理審査を受けます。また、関連学会で発表するために学生に研究費を与え、研究成果の論理的説明能力を高める機会が増えるよう支援しています。さらに、論文レビュー報告会(D1)、論文計画報告会(D1)、論文中間報告会(D2)、研究成果報告会(D3)での発表を義務づけて、発表の機会を増やすとともに、多くの教員から多様な視点からコメントをもらい、同時に研究科は各学生の研究の進捗状況をチェックしています。
3) 学修成果の評価
学修成果は、「卒業認定・学位授与の方針」に定められた項目を達成するために、学則別表や上述の学修方法・学修過程に示された科目において、目標とする学修の到達度がどの程度であったかを示すものです。したがって、学修成果となる各科目の目標はそれぞれの科目において設定しており、学修成果の評価方法も評価割合と共に科目ごとにシラバスに示しています。また、特別研究(博士学位論文)については、学生便覧に示した「博士論文審査のためのクライテリア」に基づき、指導教員以外の3名の審査委員が評価します。ここでは、論理的説明能力、研究分野に関連する幅広い専門的知識、高い倫理性等も評価されます。全ての科目は、各科目の評価方法および評価割合に基づいて、各科目の目標達成度を判断し、最終的に科目毎の成績評価を大学院履修規程の第9条に示す4段階で行います。
博士課程(後期):ディプロマポリシー
所定の年限在籍し、所定の単位を修得し、かつ以下の条件を満たす学生に、博士(看護学)あるいは博士(健康科学))を認定する。
- 学内外での研究発表の機会を通して身につけた、論理的に構成された発表およびディスカッションができるなど研究成果の論理的説明能力を有する
- 査読付き学術誌での投稿受理を必要条件とする博士論文を提出し、その学術的価値、新規性、応用的価値等を審査員が総合的に審査して、合格とする。ただし審査では、研究成果の論理的説明能力、研究分野に関連する幅広い専門的知識、高い倫理性などを有しているかも評価する。